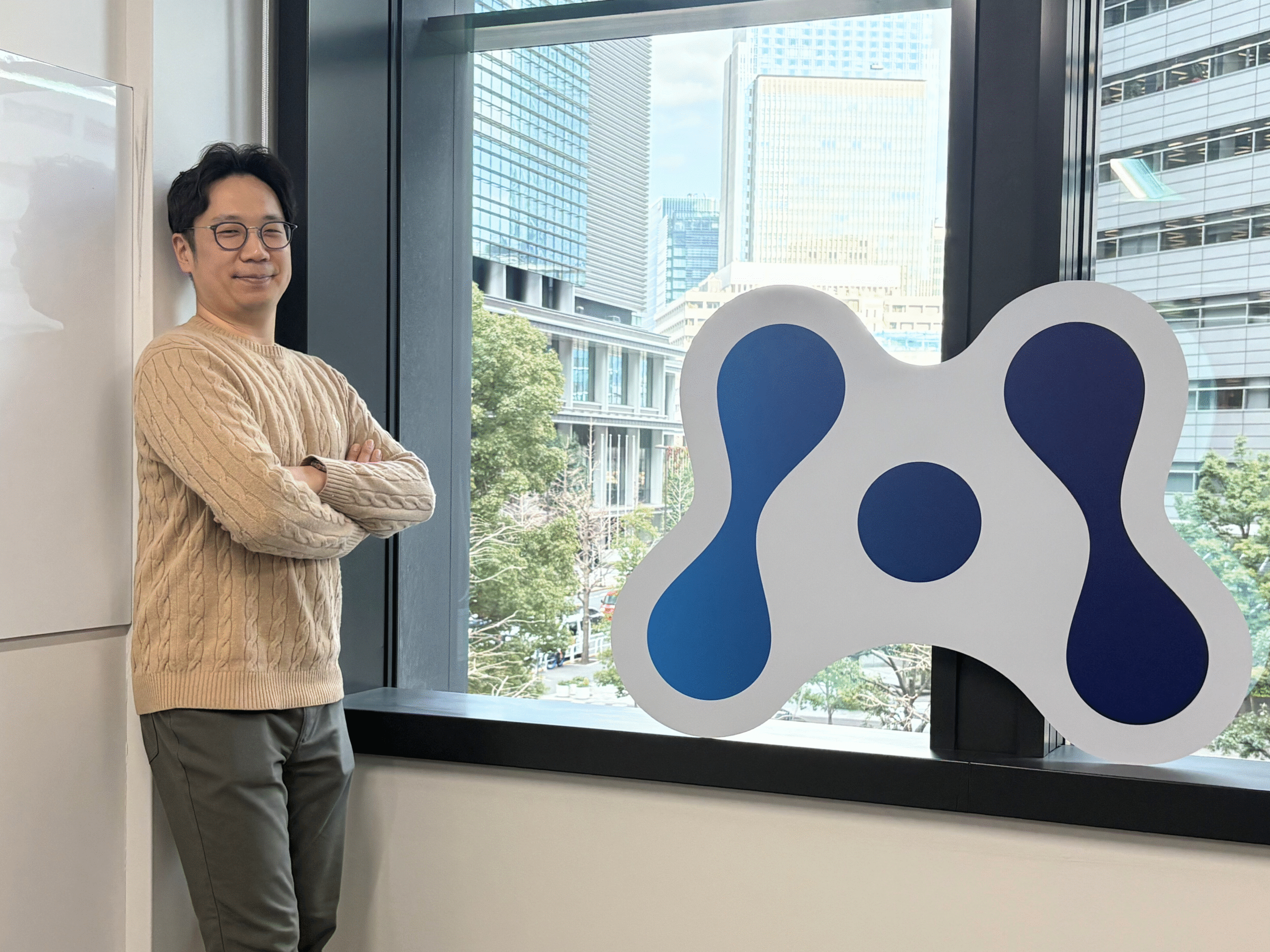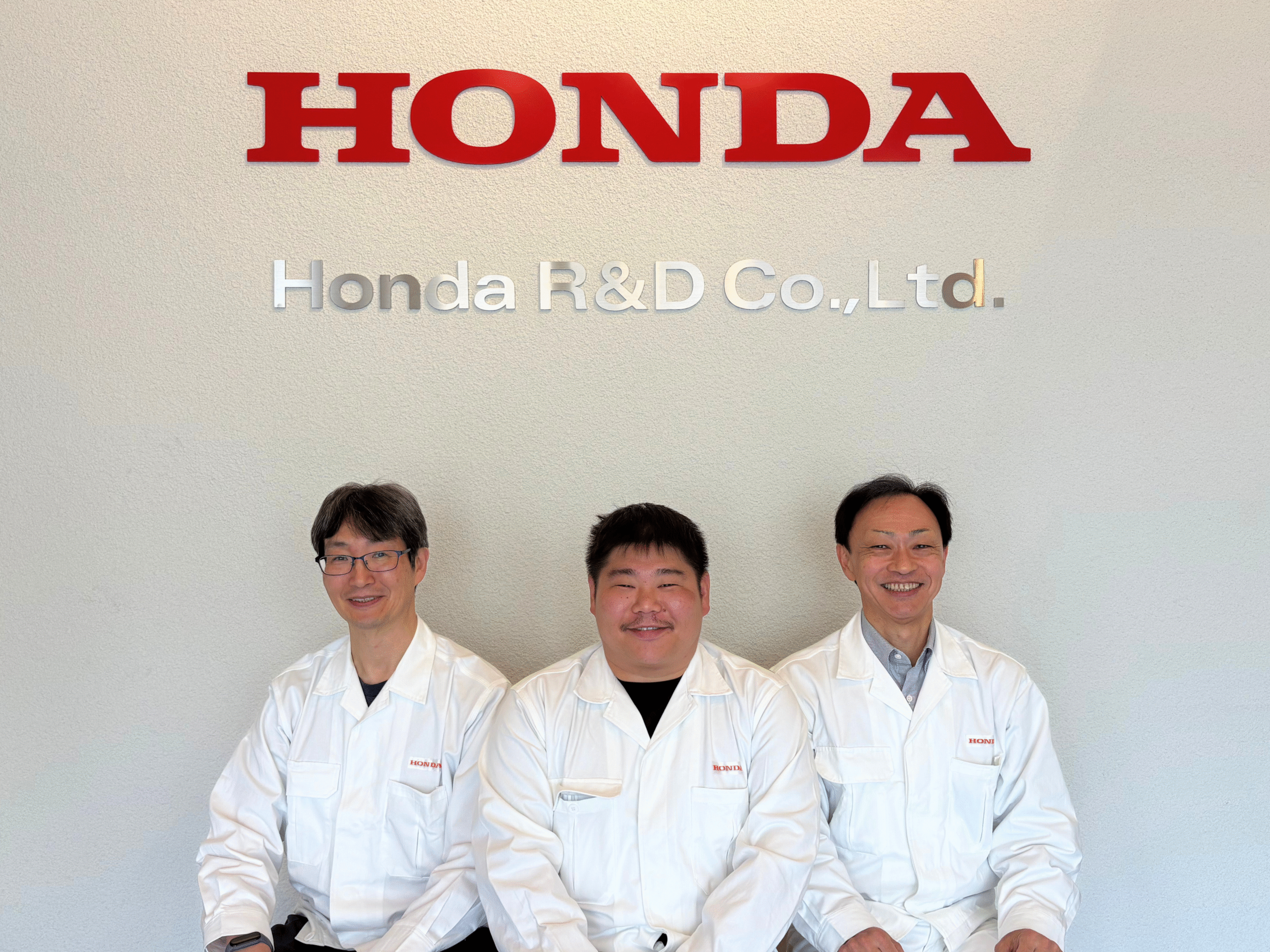東大・霜垣教授が語る Matlantis、2つのBefore/After─表面反応研究と教育を変えた「新しい研究スタイル」とは
- 東京大学・霜垣研究室
- 業種:アカデミア
- 事業内容:薄膜形成・表面反応のプロセス設計を専門とし、CVD(化学気相成長)やALD(原子層堆積)など、極微細化が進む半導体デバイス製造における薄膜成長プロセスの反応機構解析に取り組む。反応を“科学する”ことで新たな材料プロセスを設計することをテーマに、超臨界流体プロセス、選択的製膜、複合材料形成など、次世代デバイスを支える基盤技術の研究開発を牽引している。

東京大学連携研究機構マテリアルイノベーション研究センター・機構長 大学院工学系研究科マテリアル工学専攻・教授 霜垣幸浩(しもがき・ゆきひろ)工学博士
“必要なときに必要な計算が回る”世界になった。これは僕の研究人生でも非常に大きなBefore/Afterだと感じています。
極微細化が加速する半導体デバイスでは、CVD(化学気相成長)やALD(原子層堆積)といった薄膜形成プロセスの精密な制御が欠かせません。その反応機構を“科学する”ことで、新たな材料プロセスの設計に挑み続けてきたのが、東京大学・霜垣幸浩教授です。
霜垣研究室では、気相反応だけでなく、特に扱いが難しいとされる「表面反応」を対象に、実験と原子レベルシミュレーションを組み合わせた解析に取り組んできました。近年は、AI材料シミュレーションプラットフォーム「Matlantis」を本格導入し、大規模な表面モデルを用いた反応機構解析や速度論解析に挑んでいます。
その結果、研究室には2つの大きなBefore/Afterが生まれました。ひとつは、これまで“ほぼ不可能”とされていた表面反応の速度論解析が、現実的な時間スケールで回り始めたこと。もうひとつは、学生教育のスタイルが根本から変わったことです。本記事では、霜垣教授が語る「MatlantisがもたらしたBefore/After」を紹介します。
※本記事では、一般に用いられる「成膜」ではなく、「製膜」という表記を用いています。霜垣先生は、薄膜形成を、膜が自然に「成る」現象ではなく、反応のメカニズムを理解したうえで、プロセスを設計し、狙って膜を作る行為だと捉えています。この表現には、東京大学電子工学専攻の多田邦雄先生からかけられた「設計して狙ったものを作る行為は“製造”でしょう。ならば、薄膜研究は“製膜”ですよね」という言葉が背景にあり、霜垣先生はこの考え方を今も大切にされています。
気相では実現した“実験→計算”の大転換が、表面反応ではなかなか起こせなかった
Q 先生がテーマとされている気相反応と表面反応では、解析の難しさが大きく違うと伺いました。まず、その背景から教えていただけますか。
霜垣先生:
そうですね。まず気相反応について言うと、これはもう計算でどんどん突き詰めることができる世界になってきました。一方、表面反応となると話がまったく逆なんです。
量子化学計算で気相反応速度が「1」と出てきたとして、実際の反応速度は「0.1〜10のどこかだろう」と幅を持って扱うことができる。しかし表面反応においては、量子化学計算で求めた反応速度が同じ「1」と出てきた場合でも、1000かもしれないし、1000分の1かもしれない。もっと外側かもしれない。
つまり、「計算値そのものを信頼して研究を進められる世界ではない。結局、実測しないといけない。」というのが長年の現実でした。
僕らは最終的にrate constant(速度定数)を知りたいわけですが、これは吸着状態を計算して終わりではなく、遷移状態の探索、振動解析、分配関数の導出……と段階を踏んで求める必要があります。
そこで効いてくるのが、「大規模モデルが必要なのに、DFTでは扱いきれない」という問題です。
一般に使われる表面モデルは一辺0.5~1 nm程度のエリアの小さなセルです。これだと周期境界条件の影響で、分子が1個来たら、表面全体に“一斉に”来たような計算になってしまう。
本当の現象はもっと希薄で、10×10の表面に1個来るか来ないか──そんなドーピングや吸着の違いが、製膜速度や膜厚分布に大きく効いています。
たとえば一酸化炭素分子(CO)の吸着でも同じで、金属表面にCOが吸着していくと、60%までは分子同士がほぼ独立に振る舞いますが、70%を超えると隣接分子の反発や相互作用で吸着エネルギーそのものが変わってしまう。こうした“被覆率依存”の挙動は、小さなセルでは再現できず、大きなスケールでないと本質を掴めません。だから小さなセルで計算しても、本質は見えない。
僕が表面反応に対して原子レベルシミュレーションを使うときにずっと言い続けてきたのは、「大規模でやらなきゃ意味がない」ということです。感覚的には一辺数nmのエリアは最低限、できれば一辺5 nm以上の大きさが欲しい。
しかしそんなものをDFTで回そうとすれば、もはや現実的ではありません。東大のスパコンでも、少し大きくするだけで計算時間は何十時間、場合によっては何百時間にもなる。研究室でもメモリ1 TB、64コア×2のワークステーションを500万円かけて導入しましたが、実際には「大規模計算は“できる”けれど、“回る”とは言えない。」という状態だったんです。
さらに厄介なのは、そこから速度論まで落とし込む工程の重さです。吸着状態を計算し、遷移状態を探し、振動解析をして、分配関数を導出し、そこからrate constantを求める。この一連の計算を大規模モデルでやるのは、従来のDFTではほぼ不可能に近い。
だから僕はずっとこう思っていました。「気相では1990〜2000年代に“実験→計算”への大転換が起きたのに、表面反応ではその革命が起きなかった。」
ショックチューブ(衝撃波管)で気相の反応速度論を実験的にやっていた研究者たちが、ある時期にショックチューブを手放してワークステーションへ置き換えていく瞬間をリアルに見てきました。でも表面反応ではそれが起きない。それは結局、「大規模モデルが必須」、「DFTでは重すぎて回らない」、「速度論まで落とすのがほぼ不可能」という構造的な壁がずっとあったからだと思います。
Q そんな状況のなかで、Matlantisとはどのような経緯で出会われたのでしょうか。
霜垣先生:
最初にMatlantisの名前を聞いたのは、元・東大総長の小宮山宏先生と研究の近況についてお話ししていたときです。その場で、「Matlantisって知ってるか?」と聞かれました。当然「いえ、知りません」と答えたのですが、先生が続けて、「Matlantisというのは、materialとAtlantisの造語らしい。どうも、非常に計算が速いらしいんだ。」とおっしゃったんです。
そのときの僕としては、「へえ、そんなものが出てきたんですね。」という程度の印象でした。自分の研究に関係してくるとは、まだまったく思っていなかった。
その後、研究会の場で別の企業研究者の方からも同じような話を耳にして、「何やら新しい計算技術が出てきているらしい」という認識だけが、少しずつ積み上がっていきました。
そして2023年、セミコンジャパンに行った際、Matlantisの方とお話しして、「あ、これがあのMatlantisか。」と、ようやく情報がつながったんですね。そこから興味が一気に現実味を帯びたのは、自分の中にずっとあった、あの構造的な問題意識のせいです。
表面反応は大規模モデルで見なければ本質が見えない。しかし、DFTでは計算が重すぎて実質的に不可能。rate constantまで落とすのはさらに無理がある。30年近く解決できなかったこの壁に、「大規模でも速いらしい」という噂が刺さったんですね。
「もしそれが本当なら、研究室の風景が変わるかもしれない。」
正直、最初はMatlantisの中身をよく理解していませんでした。ただ、当時すでに機械学習ポテンシャル(MLIP)が世界的に発展し始めていたこともあって、「気相で起きた計算革命が、表面反応にもようやく来るのかもしれない。」という感覚が、少しずつ芽生えていったのだと思います。
1つ目のBefore/After:1年かかっていた表面反応の解析が、“1週間”で回るようになった
Q 実際にMatlantisを使い始めて、研究の進め方にはどんな変化がありましたか。
霜垣先生:
最初に本格的にMatlantisを触り始めたのは、ポスドクの研究員でした。
彼はずっとSiCのCVI(ケミカルベイパーインフィルトレーション)プロセスをテーマに、企業との共同研究を14〜15年続けてきて、その中で反応機構を徹底的に掘ってきたんです。SiC 繊維は直径 10 μm 程度・長さ 1 km にもなる細い繊維を何千本も束ねて布のように織り、その「織物」の隙間にガスを染み込ませて反応させることで、軽くて耐熱性の高いセラミックスマトリックス複合材(CMC)を作る、日本でも重要な戦略材料のひとつです。
既存の反応速度論モデルパラメータモデルを調べて、「これは足りないね」という反応を一つひとつDFTで計算して補っていく。そういう作業を3年間積み上げてきました。
ただ、表面反応の部分に入ると、もうほとんど限界だったんですね。大規模表面モデルが必要になるけれど、DFTでは重すぎて回らない。吸着状態を見て終わりではなく、遷移状態を計算し、振動解析をして、分配関数を出して、そこからrate constantを落とす。この一連の計算を大きな表面モデルでやろうとすると、時間的にも計算資源的にも成り立たない。
やるべきだと分かっていても、できなかった。それが長年の現実でした。
そんなときにMatlantisを使い始めた彼が、僕のところに来て言うんです。
「先生、Matlantisだと表面振動解析もかなり楽にできますよ。ちゃんと分配関数まで計算して、rate constant に落としてみたら、実測値とけっこう合いました。」
最初は「本当にそんなことあるのか?」と思ったんです。というのも、表面で分配関数をきちんと計算して rate constant まで落とすことは、僕の感覚ではほぼ不可能に近い作業だったからです。昔から、表面反応の場合は分配関数をうまく決められなくて、結局えいやで“1”として扱うしかない、という時代が長く続いていました。
実際に彼が示してくれた計算結果では、表面振動解析から分配関数をきちんと導いて rate constant を出し、それが実測値とかなりよく合っていた。そこで僕は思いました。「ああ、これは本当に Before/After だな」と。
特に大きかったのは、エネルギープロファイルが出てくるスピードです。彼が今までに 1年や1年半かけてやっていた仕事が、2〜3日で出てきてしまう。本人も「これはもう別物だ」と言っていましたが、僕もそのスピードには本当に驚きました。以前は、吸着 → 遷移状態 → 次の安定状態へ進む“山と谷”の1枚のダイアグラムを作るのに、1〜2年かかることもあった。それが Matlantis だと 数日〜1週間でできてしまう。
さらに、ここが大きなポイントなのですが、これまで 大規模表面モデルで分配関数を計算し、速度論に落とすこと自体がほとんど不可能でした。僕自身、1990年代からそういう計算ができない状況をずっと見てきましたし、当時は気相ならできても、表面では諦めるしかなかった。吸着分子の赤外吸収スペクトルなどを参照するくらいが精いっぱいでした。ところが、Matlantis を使った彼の計算ではそれが普通に回ってしまう。「今まで不可能だったことが、普通にできてしまう」その感覚が非常に大きかったですね。
そして実験との往復のスピードも劇的に変わりました。以前は半年後に結果が返ってくる世界だったのが、いまは気になる現象があればすぐに Matlantis で表面反応解析をスキャンして、翌日には実験で確かめに行ける。
“必要なときに必要な計算が回る”世界になった。これは僕の研究人生でも非常に大きなBefore/Afterだと感じています。
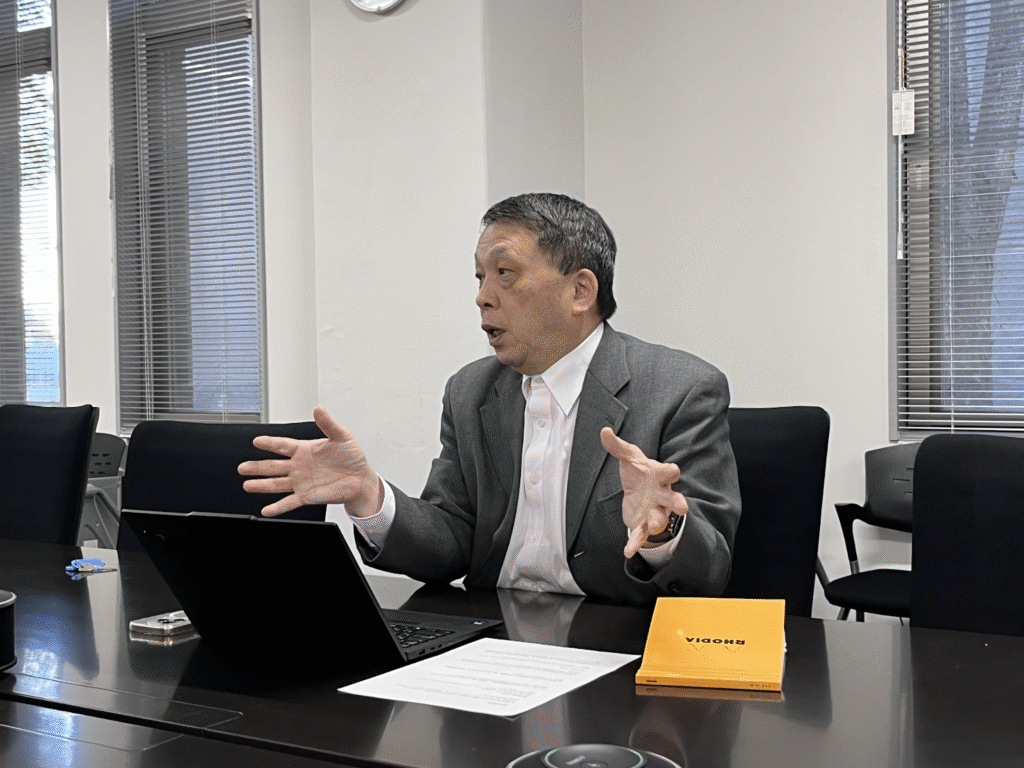
精度ではない、Matlantisの“本当の価値”
Q ここまで伺うと、「そんなに速くて本当に信用できるのか?」という意味で、精度が気になる読者も多いと思います。先生ご自身はMatlantisの精度をどう捉えていらっしゃいますか。
霜垣先生:
僕は、じつは精度についてあまりうるさく言わないタイプなんです。学会発表でも必ず「精度はどれくらいですか?」と聞かれますが、あの質問は本来ナンセンスで、たとえば吸着エネルギーが1.38 eVと出たときに±0.1 eVを許すのか、±0.3 eVを許すのか──本来は“目的に対してどの程度の誤差を許容すべきか”とセットで議論しなければ意味がありません。そもそも“真の値”は誰にも分からないし、DFT自体が複数の近似のうえに成り立つ折り合いの結果です。DFTとMatlantisが一致したからといって「誤差ゼロ」と言うのもおかしいし、実験側にも当然誤差があります。
それに、精度の議論をするときには「そもそもシミュレーションを何のために使うのか」を考える必要があります。現場で実際に薄膜を作る人たちは、シミュレーションが“100 nmになる”と言った結果が、実験で97 nmだったからといって「外れた、使えない」とは言いません。むしろ大事なのは、温度を上げれば100→120に変わる、濃度を下げれば100→80に変わる、といった“変化の傾向”が定量的に一致しているかどうかです。絶対値の90を90.5に合わせ込むような精度を追求することにどれだけ意味があるのか、僕はかなり懐疑的です。
これは創薬でも同じで、1000個の候補から1個の当たりを計算だけで引き当てるのではなく、まず1000→100→10と“絞り込む”ために計算を使う。そのうえで最後の1つを決めるのは必ず実験です。シミュレーションはあくまでも“方向を示す道具”であって、実験を置き換えるものではありません。
Matlantisの価値は、まさにこの“絞り込み”が圧倒的に速くなったことにあります。これまで1〜2年かけて描いていたエネルギー図が1週間で出てくる。表面振動解析から速度定数まで落とす作業が、研究として現実的なスピードで回り始めた。その結果、実験の設計、テーマの回し方、学生の育ち方──研究室の風景そのものが大きく変わりました。
僕にとっては、吸着エネルギーが0.1 eVずれているかどうかより、“Before Matlantis”と“After Matlantis”で研究の回り方がまったく違うという事実のほうがはるかに重要なんです。Matlantisは、現実的な時間スケールで候補を絞り込み、実験と行き来しながら現象理解を深めていくためのツールとして、十分に信頼に足る存在だと感じています。
実験×シミュレーション──これからの研究スタイル
Q Matlantisの導入で、研究スタイルそのものにも変化はありましたか。
霜垣先生:
スタイルそのものは、実はあまり変わっていないかもしれません。
さっき少し触れたように、僕自身は「昔の気相反応研究者が、ショックチューブを手放して、
すべてをワークステーションに置き換えた」みたいなことは、自分ではしないと思っています。
つまり、実験はこれからもきちんとやる。そのうえで、「原子レベルシミュレーションで現象理解を深める」という実験半分+シミュレーション半分のスタイルが、これからも基本になるだろうと思っています。
2つ目のBefore/After:B4〜M1で“実験も計算もできる研究者”が育つようになった
Q 教育・学生指導の面では、どのような変化がありましたか。
霜垣先生:
教育という面で見ても、Matlantisの影響はすごく大きいと思っています。
これまでだったら、量子化学計算をきちんと使いこなして、自分で遷移状態を見つけて、rate constantまで計算して、そこから反応モデルを構築して……というところまで行くには、正直博士課程の後半になって、やっと“勝負できるレベル”になる、という感覚でした。
卒論研究1年と修士論文研究の2年間は、基礎的なことを覚えたり、計算の流儀に慣れたり、実験の手順を覚えたりするだけで精一杯で、そこからようやく「研究を回せるようになる」まで、かなり時間がかかっていたんです。
ところが、Matlantisが入ってきてからは状況がまったく変わりました。学部4年から1年間ちゃんとMatlantisを使って、先輩に教わりながら手を動かしてきた学生が、修士に上がるころには、もう「実験半分+Matlantis半分」くらいのスタイルで、かなり戦力として動けるようになっている。これは、これまでの教育のスケール感からすると本当に異例なんです。
要するに、学生が扱える「量」が桁違いに増えたんですね。従来のDFTだと、とにかく計算が重いので、「1テーマで1〜2個の反応パスが精一杯」だったのが、Matlantisなら学生でも短期間で何十個も反応を追うことができる。
そうすると自然に、「遷移状態がどんな場所にあるのか」「どういう反応経路が出やすいのか」「表面のどこが反応しやすいのか」といった“感覚”が、学生の身体に入ってくるんです。
『量をこなせるようになると、質が変わる。』
これは昔からある言葉ですけれど、本当にその通りで、学生があっという間に「研究者の目線」に近づいていきます。僕としては、これは教育面でとても大きいと思っています。実験だけやっている学生、計算だけやっている学生、という分断があった時代から、今は「両方できる学生」が修士1年くらいで普通に育つようになった。
その結果、研究室全体としての議論の質も上がるし、実験データの見方も、計算結果の見方も、いい意味で“ハイブリッド”になってきていると感じます。
だから、教育の面でも「Before MatlantisとAfter Matlantisがはっきりある。」それが今の僕の実感です。
実験×シミュレーション×データサイエンスの時代に向けて
Q 最後に、今後の材料開発や人材育成の観点から、Matlantisのようなツールに期待することを教えてください。
霜垣先生:
今後、材料開発の世界は間違いなく、実験×シミュレーション×データサイエンスの三位一体で進んでいくと思います。
今は、データサイエンティストの方々が実験データを機械学習にかけて、装置条件やプロセス条件の最適化を図る、ということをいろんなところでやっていますよね。ただ、そのときに「プロセスの物理・化学の中身をどこまで理解しているか」というと、まだ道半ばな部分も多い。
これから必要になってくるのは、おそらく「プロセスサイエンティスト兼データサイエンティスト」のような人材だと思っています。
そういう人たちは、きっと片手にMatlantisのような原子レベルシミュレーションのツールを持ち、もう片方の手にビッグデータ解析やシンボリック回帰のようなツールを持って仕事をする。
Matlantisのようなツールで、吸着自由エネルギー、被覆率依存性、温度依存性といったデータを大量にサンプリングしておいて、そこからシンプルで汎用性の高い経験式やモデルに落とし込む。そういう「橋渡し役」としても、Matlantisには大きな役割があると感じています。
その意味で、研究の面でも教育の面でも、「Before Matlantis/After Matlantis」という二つの世界が、はっきり分かれつつある。今回お話しした2つのBefore/Afterは、その一部にすぎないのかもしれません。
本事例の公開日:2026.01.06